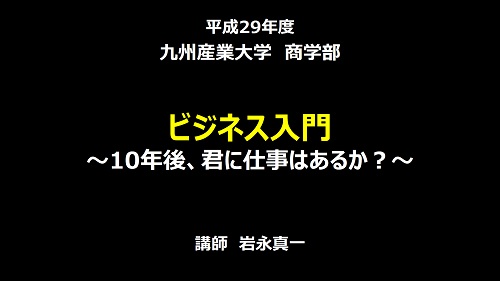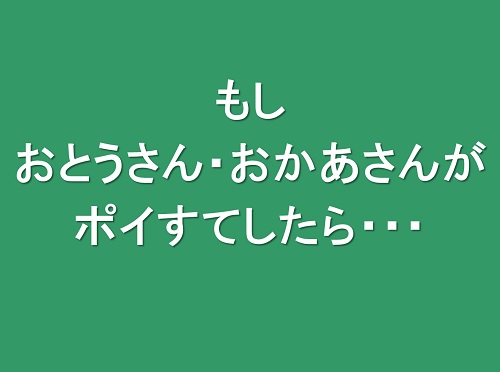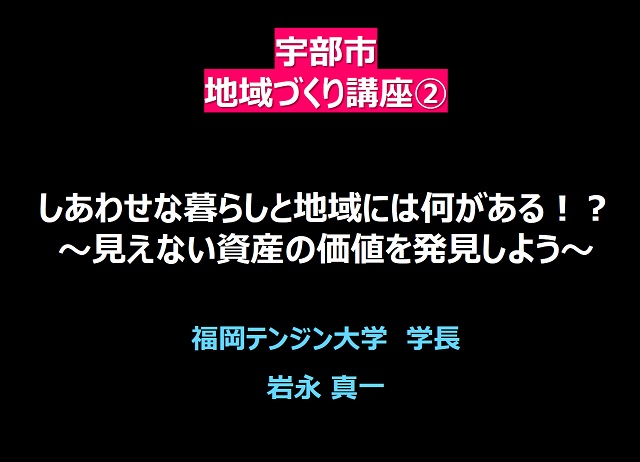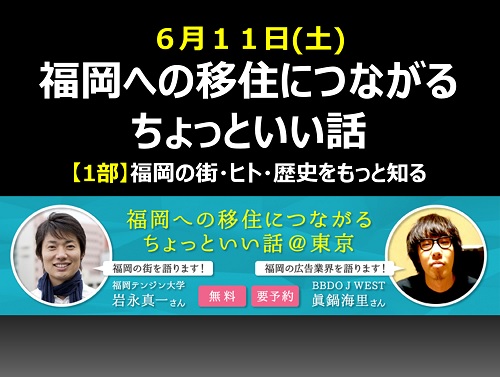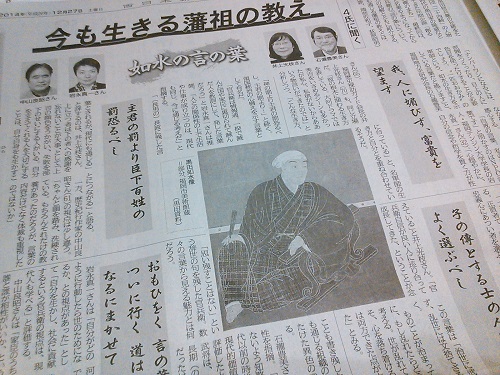これまで福岡県内のいくつかの大学で授業をしたことがあります。「地域活動の実践型プロジェクトを、教育プログラム化して提供する」という北九州市立大学の先生以外、九州大学や福岡大学、福岡女子大学、九州産業大学、福岡県立大学と、これまで「単位」を付与するというか、成績付けまでやる、つまりシラバスまでつくる授業をしたことはありませんでした。
この秋より後期の、九州産業大学・商学部1年生の必修科目「ビジネス入門」の担当をすることになり、毎週木曜日は丸1日かけて(通称)九産大に通っています。
ビジネス入門の授業の構成やシラバスは?
数年前より自分に相談が来るあらゆる仕事を、「なぜ?」「これはどんな意味がある?」「街や社会にどんな価値を提供できる?」を自分なりにしっかり言語化して、自分の中に腹落ちさせないと実行しないようにしています。そして今回の九産大のビジネス入門も、「なぜ外部の講師なのか?」「なぜサラリーマンじゃない、事業家・起業家とも違う、どちらかというとソーシャル寄りな岩永なのか?」と、かなり頭の中で思考して自分なりに言語化しました。
そして組み立てていった結果出てきたのがサブタイトル「10年後、君に仕事はあるのか?」。
僕に授業をお願いするってことは、中高生夢チャレンジ大学で次世代人材育成の先端を知り、(福岡という地方だけど)いろんな業界に顔を出し、主に広告業界寄りのコンサル(マーケティング的なものがほとんど)もしているし、リーダーシップとかコミュニケーションとかの研修・授業もやっているし、という点なんだと確信。そして、これまで自分が社会人生活13年で培ってきたことや、教えられる知識(とその組み合わせ・使い方)、さらに「学び方の学び方」、「これからの時代を見る目」を養うような内容で、自分ができるあらゆるものを詰め込みました。ファシリテーションの視点をあらゆる現場に入れているので、この授業でも「どう学びを促すか?」の視点で企画段階から自分なりのメソッドを詰め込みました。
その結果、シラバスはこのように。(授業を進めながら少しずつ変化中、今後も変わるかも)
①オリエンテーション
・講師紹介、講義のゴールと進め方、自己紹介
・正解が1つじゃな時代の到来
・物事を分解してみる、分解すると仮説が立てやすくなる
②お金の正体
・お金のはじまり、お金の価値と正体
・価値はどうやったら生まれる?
・経営資源(ひと・もの・かね・情報)
③テクノロジーの進化に驚愕する
・AI、ロボットの進化スピードと現在地
・IoTの可能性、ブロックチェーンと仮想通貨
・AIやロボットと共存するための力とは
④日本ってこれからどうなる?
・世界から見た日本ってどんな特徴?
・親の若い頃の時代と、今の君たちは真逆の環境を生きてる
・人口問題、正社員や非正規、社会が激変する時代を生き抜くには
⑤ビジネスの仕組みを知る
・企業の数・中小企業の数、就活で出会える会社数は?
・どんな業界にどんな仕事がありそうか?
・BtoB、BtoCを知る、福岡にもある日本一の企業
⑥マーケット感覚を養う
・マーケット感覚で社会の見え方を鮮明にする
・価値をより価値あるものにするマーケティング
・これからのビジネスが向かう方向性とソーシャルビジネス
⑦プロフェッショナルの仕事
※福岡の広告業界よりゲスト
⑧プロフェッショナルの仕事
※福岡の田舎に移住したゲスト
⑨プロフェッショナルの仕事
※事業を多角的に展開したゲスト
⑩リーダーシップ開発
・自分の思考のクセを知ろう、自分のアイデンティティの源泉を探ろう
・コミュニケーションって?
・自分のコミュニケーションスタイルを知ろう
⑫リーダーシップ開発
・これまでの人生を振り返る、自分の価値観を知ろう
・自分のリーダーシップ・個性を知ろう
・人間関係構築力、チームワーク力
⑬リーダーシップ開発
・アイデアを形にする力、ロジカルシンキングを鍛える
・企画力を鍛える、キャッチコピーをつくる
・プレゼンテーション
⑭10年後、君に仕事はあるのか?
※福岡の起業家とも親交あるビジネスマンをゲスト
⑮ビジネス入門を経て
これまでのリフレクション、体験の言語化
という計15回の授業になります。
大講義室に大人数なためいろいろと実験中
僕はこれまで多くても40人くらいの研修での講師が多かったのですが、今回の授業の対象者は九産大の商学部1年生全員、その数約700名!はい、そんな大人数がいっぺんに入る講義室はないので、これを3つに分けて約200名ずつくらいを毎週木曜日にやっています。つまり同じ内容を3回、計15回ずつあるので合計45回ですね。これ、めちゃくちゃたいへんです。何がたいへんかって「成績付け」です。もちろん学生たちの顔と名前は一致しないし、誰が誰なんて覚えられません。。。
さらに教室は、昔ながらのステップ(階段)になってる緩い傾斜の机と椅子が固定の講義室です。
僕が一番やりたい「学生同士の対話」なんてやりようがない。現場でのファシリテーターらしきコンテンツやテクニックはなかなかやりようがない。しかも必修科目だし、男子の多い九産大だし、受講態度は期待できない(ご想像ください)。
さて、こんな中でいろいろ試行錯誤を重ねています。まず「正解が1つではない問い」を毎授業で1~2問出題。1回目授業では4人1組を作らせて「問い」を投げかけグループワークを試みたものの、大半が友だち同士で座っているので、回答はあるものの、グループワークあんまり効果なし。3回目よりグループワーク後にランダムに当てて、その当たった学生がいるグループのリーダー役が回答するというスタイルに、でもあんまり効果なし。4回目からグループをつくるのは強制せず、自分で考えたり&まわりと相談しあってOKにし、ランダムに当ててその学生に回答をもらい、回答した学生には加点することに、これもなんかしっくりこず。ただ、ランダムに当てられて「答えられなかったら欠席扱いにする」(だって、回答しない、イコールいないのと同義)と通達、すると「考える時間」は一応、みんな考えてるフリはできるようで。
5回目の授業で「問い」を出したときに、自分で考えてもOK&まわりと相談しあってOK&スマホで調べてもOK、としたところ多くの学生がスマホ出して調べる。おっ、なんか違うぞ。毎回、正解が1つじゃない、考えたり調べたり「とにかく出す」とどれもが正解な問いしか出してないのですが、この「自分で調べる」という行為が大当たりっぽい。
授業毎にリフレクションをスマホで回答!
今どきの大学生は手書きの文章より、スマホでテキストを打つ方が早いし慣れてる!それにこれからの社会は、そして卒業して社会人になったら、なおさら手書きよりPCなどでテキスト打つことが主流なのに、わざわざ手書きさせる必要ないな(卒論もPCで打ち込むだろうし)というのは建前で・・・。実際は700名近くいると「成績付け」が超苦労しそうなのがわかってるので、授業ごとにデータベースを用意し、フォームを作成して「スマホでアクセスして回答」できるようなものを作りました。
回答はリアルタイムにデータベースにたまり、学生の個人情報と紐づいて回答できるようにしてるので、「管理が圧倒的に楽」です。というか大人数の授業ではこんなことしないと生産性上がるわけないですね、全国の大学の先生たち、未だに手書きレポートとかで消耗してるのかな・・・。
で、僕が行っているのは毎授業「その授業に関するリフレクションになるような問いについて書く」です。この授業のゴールの1つに「思考の言語化を鍛える」を置いていて、それが毎授業体験できるようにしているのですが、(欠席者がある程度いるので)600名近くの回答をほぼすべて目を通すようにしてます(とは言え1人30秒でも300分、5時間、そんな時間ない!だから1人10秒ちょい、だいぶ速読鍛えられます)。
大人数でも思考の言語化を鍛え、学び合いも起こせる!
当初の計画には入れてなかったのですが、リフレクションで「これはなかなかイイ回答だな」と思うものが出てくる、それを次の授業で共有しようと、ほぼそのままの形で名前がわからないように紹介するようにしました。どんな表現が良かったかなど思考を言語化できてた部分を評価というか、こうゆうのはすばらしいですね、建前でもこう書けることはいいですね、と誉めます。するとどうでしょう、それが「良い回答の例」になるのか、多くの学生が引っ張られることが確認できました。
4回目、5回目になると「言語化」が全体的に向上してるのがわかります。この授業、1授業あたりの講師代が決まっていて、たいへんな割りに予算低い(来年度も同じ内容で相談されたら断る、初めてだったし、自分も勉強になると思って受けた)のですが、アシスタント(テン大スタッフで比較的フリーに動ける人)を自腹でつけていて、そのアシスタントも「回を追うごとにみんな言語化が上手くなってる」と言ってます。
さらには「こう思うのですが、どうでしょうか?」と質問してくる学生がついに現れ!それに次の授業で回答し、他の学生にも勉強になるようにいろんな情報をくっ付けて紹介。これって直接ではないけど、しっかり学生とコミュニケーションしてますよね(名前はわかってるけど顔がわからない気持ち悪さは残りますが)。
授業中に「スマホで調べる」をOKにしたらこんな効果も!
で、5回目のリフレクションのときに「授業には関係ないけど、授業で教えた思考をもとに、普段の生活でどんなことに意識を向けられそうか?」みたいな問いにしたら、けっこうみんなしっかり「考えたこと」を書けるようになってきました。そして5回目の授業でやった「スマホで調べてOK」の効果がこのとき大いにみられたのです!!
授業中の問いは「B to B のビジネスをしている業界・企業・サービスなどにはどんなものがあるか?」です。多くの学生がスマホで調べていました。
そして5回目の授業の最後に書いてもらうリフレクションに「B to Bについて調べていたら」という文言とともに「こんな情報が出てきて驚いた」とか「意外だった」とか「知れて自分が全然知らないことを認識した」とかの文字がたくさん並んでいるのです。中には「ホワイト企業が多いと書いてあって、もっと知りたくなりました」という回答もちょこちょこありました。
誰が当てられるかわからない(強制的に当てて発表させるので)という強制力(ムチ)と、回答した学生には加点(アメ)する、そして周りと相談しあってもいいし、スマホで調べてもいいというのが、思った以上に効果があったようです。
「問い」の設定ももちろんありますが、これらの組み合わせが大人数でも「効く」ことがわかってきたので、どんどんやってみようと思います!15回終わって、約700人のうち、5%の35~50人くらいでも「学び方の学び方」を習得して自走しはじめる学生が出てきたらもう十分かと。
きっと、他の大学にもなっかなかない、大人数ながらの「社会の仕組み」や「思考の言語化」そして「自分のリーダーシップやコミュニケーション」を知ることができるビジネス入門になってきてます!!リフレクションを読んで効果が出始めているので、「授業という現場」だけがファシリテーションじゃねーな!と実験が上手くいっていてモチベーションが一気に上がってきました!
これからの、教育・人材育成におけるラーニングファシリテーターってこういう仕事になっていくんだろうなぁと実感中です。