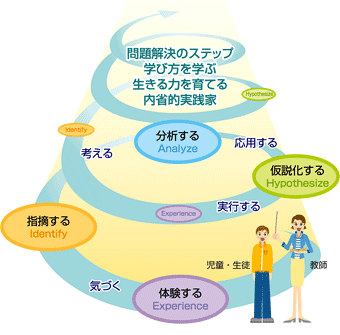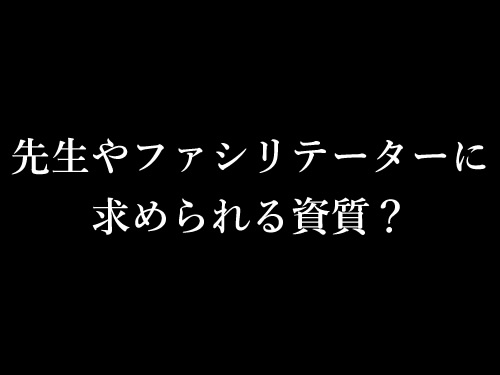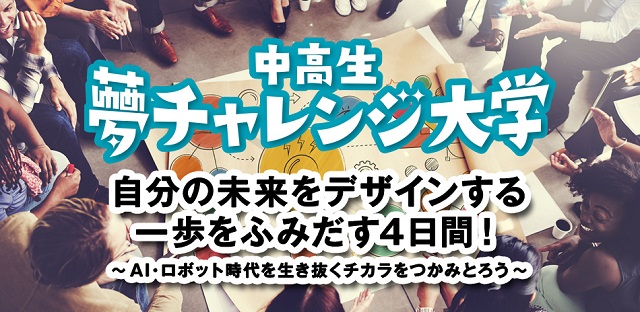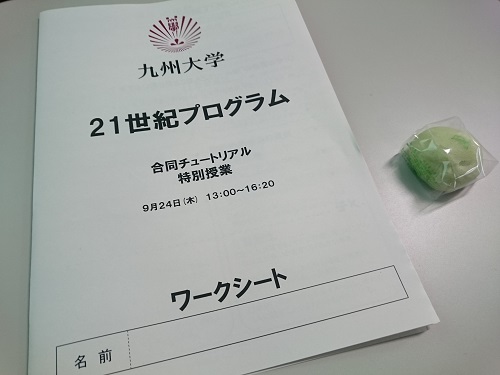いま、日本の教育業界が揺れていますね。大学入学者選抜と高校・大学教育の一体的改革を検討する中央教育審議会なるものが開かれていますが、「入試」がいよいよ変わろうとしてますね。受験のための教育と言ってもいいような知識教育を受けている中学生・高校生に毎年教える機会もありますが、頭の中にある自分の感情・考えを、口に出して言語化する訓練が全くされていないことに気づきます。
インプットのみだと答案用紙の戦いになる
今までの教育は大学も含めて、知識提供型の教育でした。それが最近、「それだけじゃ学習効果が低いよね」という考え方が入ってきて、急に「ファシリテーター」なんて言葉も教育業界の中で言われるようになってきています。実際に、福岡県内のいくつかの大学に講義でおじゃまするのですが、その大学や学部によって教育方法が若干異なるので、やはり講義の内容は全然違うものになります。
いまだに知識提供型の教育で、テストも暗記したもののペーパーになっている大学は、その学生の質がすぐにわかります。頭の中にある自分の考えを言葉に出す機会が乏しいため、他人と1つのモノゴトに対して、議論をしながら深めていく、という行為がなかなかできません。つまり、アウトプットの機会がないのです。
残念ながら、アウトプットの機会がないと「自分で考える」ということはできても、他人と共有したり、行動に移す過程を学べないため、どうしても受動的な態度・学びになり、それがまた後の人生の選択肢に反映されていきます。そんな大学の先生たちの嘆きもよく聞きます。。。
しかしアウトプットばかり学んでもダメ
Huffingtonpost(ハフィントンポスト)に、以下のような記事を見つけ、その通りだと思いました。こちらの記事に登場するこの部分、
かつての日本はインプットが重視されすぎていたのかもしれません。知識がある人は多いけれど、知識を生かせてないという反省からか、日本の教育はアウトプット重視に変わってきました。アウトプットの重要性を認識するのは良いのですが、それもインプットが十分に行われることが前提です。
確かにここ近年、インプットがないのにいろいろと社会活動しすぎている大学生も多い気がします。と言っても、自分もそんな大学4年生を送り、卒業後もアウトプットばかり気にしていた社会人だったような気がします(笑)。とは言え、大学4年次より読書量を増やし、社会人になって多様な人と出会う機会を得て、26歳ごろからインプットとアウトプットのバランスが上手に取れ始めたのを感じました。結果が出始めたんです。
アウトプットもセットに教育
冒頭のイラストは、たまたま南山大学のHPで見つけて、要点がキレイにわかりやすく図になっているので引用しました。
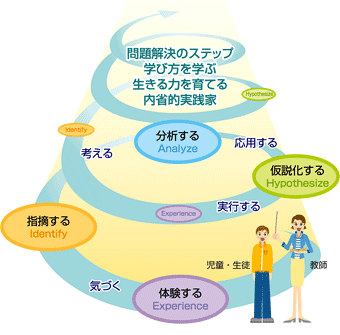
(南山大学HPより引用)
まさにこのサイクルを上手に回すことで、「学び方の学び方」をしっかりと学び、問題解決能力を向上させていくこと。インプットがある前提で、アウトプットを行い、さらに振り返ることで足りないインプットを補っていき、そしてまたアウトプットの繰り返し。これはまさに自分自身が、社会人になってボランティア活動を通して実践してきたサイクルだな、と思ったのです。
足りてないアウトプットの場
アウトプットばかりしていてはダメだ、という批判もその通りですが、どちらにしろ今までがインプット重視の教育で日本全体を作ってきちゃったので、アウトプットの場はまだまだ足りてないですし、それを促すことができる教育者や人材育成の人材も足りていません。今後は、インプットも促せて、アウトプットも促すことができる人材がどの業界でも必要になってきます。1人でできなければ、2人以上で組んでそんな場づくりが出てくるでしょう。
現に出てきていますね。いろんな大学が外部に講師を求め始めています。修士も出ていない、教員免許もない、教歴もなかった僕が、まちづくり活動・ボランティア活動の実践およびファシリテーターの現場の経験というだけで、県内の大学に呼ばれたり、公民館に呼ばれたり、他県からも生涯学習や地域づくり・人づくりなんかでたまに声かけていただけるのかもしれません。
今思えばですが、僕の場合は「テンジン大学」が圧倒的なアウトプットの場になっていることも事実で、今この場を数名の授業コーディネーターが何度も経験を重ねていってるので、確実に成長が見えます。さらにこのコーディネーターの1人が、10年近くやってきているこの福岡のとあるプロジェクトにも、新しい風を起こしているということも生まれてきました!まさに、インプット×アウトプットは、確かに人を成長させますね。