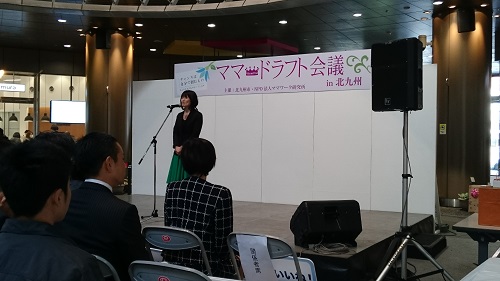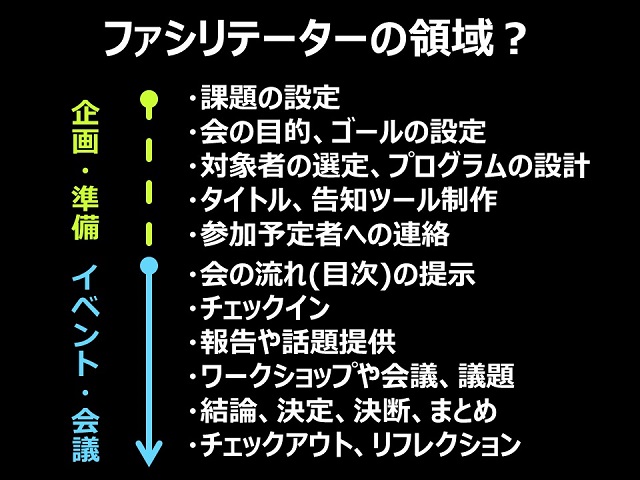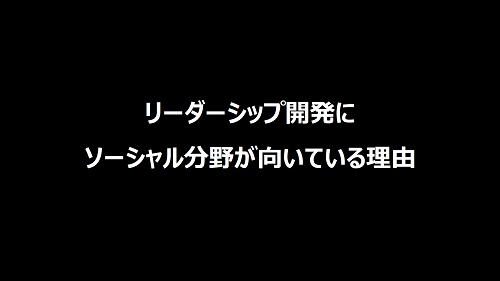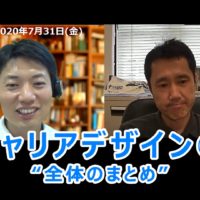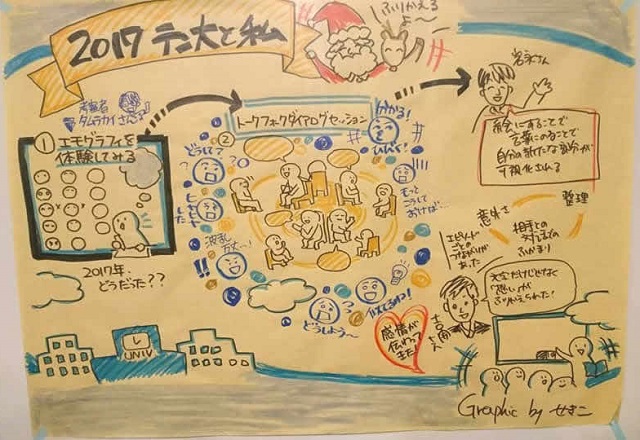2025年1月に発売される月刊『先端教育』(2月号)が、福岡県特集をするそうです!それに伴い、「福岡テンジン大学と岩永さんが実践している複業や“学びの場づくり”」についてお聞きしたいと連絡いただき、インタビューを受けました。見開き2ページに渡り掲載されるそうで、タイトルにある「地域を舞台にした学び」がテーマです。私が近年考えていたことをお話ししたところ、取り上げてもらえることになり、編集長と話していたのが「少し尖った内容になっている」と双方とも思っていたので、読んだ方の反応が楽しみなところです。
冒頭の写真は、先月11月23日(祝)に福岡県の朝倉にある寺内ダムへ、福岡都市圏の水源地を巡り「水を巡る暮らし学ぶ」バスツアーを、福岡地区水道企業団と福岡テンジン大学で企画したときのものです。水をもらう側(福岡都市圏)と、水を提供する側(朝倉の地元の方々)と、この自然からもたらされる「水」(恵みでもあり、ときに禍でもあり)について、対話をしながら学び合う場もつくれて良い場になりました。
月刊『先端教育』で話した内容とは
この雑誌は全国の大きな書店で販売され、少し早めの12月27日以降に書店に並び始めるそうです。発行部数は5万部で、全国の教育関係者や人材育成、教育行政に関わる方が読んでいるかもしれません。インタビューでは以下の項目について聞かれました。
- ・福岡テンジン大学について
- ・地域を舞台にした学びの可能性について
- ・学びの場の設計について
- ・今後、教育分野で取り組みたいこと
福岡テンジン大学についてはこれまでにもメディアで取り上げられてきましたが、「地域を舞台にした学びの可能性」や「学びの場の設計」について取材されたのは初めてでした。自分なりに体系化&言語化する良い機会となりました。
今回は、特に「地域を舞台にした学びの可能性」について書いてみたいと思います。(記事には多くのボリュームで書かれないと思うので、詳細を記しておきます)
参考:先端教育オンライン
「地域を舞台にした学び」が持つ可能性とは?
「学び」というと、多くの人は学校をイメージします。文科省も「学校と地域でつくる 学びの未来」というWEBサイトを展開しており、初等教育の「総合学習」や中等教育の「探求学習」では、学校の外の地域を学習に取り入れ、その先にある社会と学びを接続する役割があります。
今回の『先端教育』で話した「地域を舞台にした学び」は、大人も含めた全世代に対する学びの可能性についてです。
この10年ほど、国策として「地方創生」が進められ、各地方自治体では「まちのことを知ってもらう」ための施策が行われています。人口流出を食い止め、若者を呼び込むための移住政策や交流を生み出して関係人口を増やす取り組みなどが進められています。
しかし、ここで言う「地域を舞台にした学び」はこれらではありません。地域のことを知ってもらうだけならSNSに強いインフルエンサーと組む方が効率的です。知ってもらうことを第一目的とした施策としては、「学び」は非効率です。
2020年からのコロナ禍以降、オンラインの世界だけで生計を立てる個人、いわゆるSNSをハックしたYoutuberやInstagramerなどのインフルエンサーが激増して、それに憧れる子ども・若者・大人も増えたことがまず1つ。そしてこの数年で多拠点居住をする人が注目されていることと、コロナ禍中は「人に会わないこと」が是とされていた時期に、オンラインゲームやプラットフォームで「繋がった人たち」とばかりコミュニケーション取る人が増えたことが1つ。これらの現象をもとに「地域を舞台にした学び」の可能性を、自分の中では「アイデンティティを確認する場」でもある、と定義するようになってきました。
『天空の城ラピュタ』が示す“土から離れては生きられない”
知り合いのとある大学の先生の息子さんは、小学1年生のときからオンラインゲームのフォートナイトにハマり、平日でも朝5時30分ごろに起きてフォートナイトに繋いで、ゲーム内で繋がった友人たちとゲームをして、その後朝ごはんを食べて学校へ行く。そして帰ってきてまたフォートナイトに繋いで友人たちと遊ぶ、という日常になっていたそうです。
しかし、とある発言にドキっとしました。
「一緒に遊んでいた1人が、あるタイミングからゲームに入って来なくなった。一瞬心配していたが、その後誰も気に留めることなく、その人のことを心配することもなく、またゲーム上で繋いで遊んでいる。」と。
このとき、自分が何者であるか?という「アイデンティティ」を、オンラインという無重力の仮想空間内に形成してしまうことの脆さに、ドキっとしました。
オンラインが登場する前、人は「自分が何者であるか?」のアイデンティティを、「自分がどこで生まれて、誰の子どもで、誰とともに遊んで、どんな先生のもとで学んで、どんな経験をして、どんな感情を味わったか。そしてどの組織に所属し、何をしている人か。」という、ほとんどが「その地域・土地に根差した“何か”との繋がり」の中に、自己を形成していくのが当然でした。
ところが、オンラインが登場し、その仮想空間で過ごす時間が長くなったり、その空間上で出来た人間関係でコミュニケーションを取る時間が長くなると・・・。地域・土地に紐づいていない、そして“何か”が定義しづらいものの中で、自己を形成しなければなりません。それがゲームであれば、ゲーム開発会社が作ったパターンの組み合わせの中でしか自己を形成できません。SNSであれば、その中で自分が発言した内容やアップした写真・動画の中で、アイデンティティが形成されていきます。
要するに、「自分が何者であるか?」というアイデンティティは、リアルでもオンラインでも、自分と“何か”(多くの場合は他者)との関係性の中に築かれるものです。
ところが、オンライン空間は無重力であり、人工的な空間であり、イレギュラーなことが起きにくい、リアルよりも情報量が少ない(五感で得られるという意味で)、さらに「削除」することも「上書き」することもできる空間です。つまり根が生やせない。 これだけ情報化が進んだ社会に生きている人類の中でも、常時オンラインに接続している我々は、自己のアイデンティティ形成を「地域・土地」から離れた空間で形成してしまうことのリスクを抱えてしまっていることを、近年モヤモヤと考えていました。
そこで繋がったのが、ジブリの『天空の城ラピュタ』に出て来る、シータの発言「人は、土から離れては生きられないのよ」でした。
地域を舞台にした学びは、アイデンティティを確認する機会になる
これだけオンラインで過ごす時間や、コミュニケーションや人間関係構築をオンラインで行う時代になって、1つ疑問に思っていたことが今回のことで繋がりました。それは、日本の子どもの人口は明確に減少しているのに、子どもの引きこもり・不登校の増加です。コロナ禍でさらに数が増えているのを知り・・・
「地域・土地に根差した様々なヒトやコトと、コミュニケーションを取って、関係構築する機会が減った」からではないか、という仮説を強く思うようになりました。これは子どもだけの話ではなく、大人にとっても「地域や土地と繋がる機会」が減ると、アイデンティティを確認する機会が失われます。
やれ「●●会社の部長だ」「●●で役員をしている」などの所属組織の肩書の中に、自己のアイデンティティを見出そうとするため、引退したあとに肩書が消えてもアイデンティティを元いた組織の肩書に求める男性が現れるのは、その証左だと思います。
しかし!地域を舞台にした学びは、リアルでその土地に立ち、テーマごとに“それ”に興味のある人同士が集まるため、「自分がどこに暮らし、地域の何に興味を持ち、同じように興味を持った人たちと交流することで新しい出会いや活動が生まれる」ことに繋がります。それは、「削除」や「上書き」がされにくい土地が持つ情報と結びつきができ、実際に「その環境の中にいる自分」という、根の生えたアイデンティティを形成することに繋がるのでは?と。
地域を舞台にした学びは、本来の人間性を取り戻す活動であり、そんな学びや活動があふれた地域は「人との交流も盛んで、多くの地域の情報が共有・発信される」ため、地方を活性化する土台となるのではないか?そんなことを考えながら今回の取材でお話ししました。
天空の城『ラピュタ』からは人間はいなくなった
ジブリのラピュタの世界では、土から離れて強大な力を持った人たちは「滅んだ」ことになっています。そのラピュタでは、無人ながらもロボットだけが守る世界に・・・。
宮崎駿さんがラピュタを通して言いたかったメッセージを、近年はこのように受け取るようになりました。
『今は、ラピュタがなぜ滅びたのかあたしよく分かる。ゴンドアの谷の歌にあるもの。”土に根をおろし、風とともに生きよう。種とともに冬を越え、鳥とともに春を歌おう”。どんなに恐ろしい武器を持っても、たくさんの可哀想なロボットを操っても、土から離れては生きられないのよ』
「地域を舞台にした学び」の場は、個人も地域も持続可能にする手段の1つであり、「アイデンティティを確認・蓄積」しうる場になる。
そんなことをモヤモヤと考えていたことを、今回の取材を通して言語化して話せた良い機会になりました。改めて、声かけくださった月刊『先端教育』の伊藤編集長に、この場を借りてお礼としたいと思います。