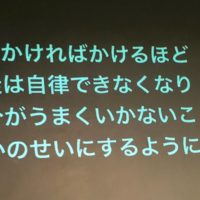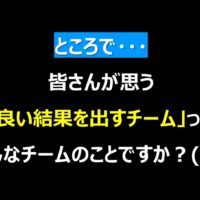2023年も残り3カ月半となるも、毎年次々に多方面からの相談をいただき、仕事としてのアウトプットに追われる日々。とくに今年はGW明けからの(コロナ禍が終わりを告げた)タイミングで、「人が集められる」スイッチが入ったのか、講演・ファシリテーターの相談を多くいただいております。
岩永真一という“個”と、その“個”が持つネットワークから来る「知恵・アイデア・コミュニケーション」に期待を持って相談いただけることが何より嬉しく、それに応える日々で、体験したこと&思考したことを整理する機会を失っておりました。
久々に筆を取ろう(正確にはPCと睨めっこしてタイピングしよう)と思い、ここ1カ月で体験したことが全て「●●づくり」に関することだったので、ふりかえりを込めて言語化してみようと思います。
企業経営から都市経営まで「人の営み」をよりよいものにしたい
ここ5年、複数社の企業経営にも携わる機会を得ることができ、また20年近くまちづくりのような地域づくり・まちづくり・エリアマネジメントにも関わってきたものが、頭の中で急速に体系化されてきています。
その結果、現在の岩永真一としての仕事の方向性は、上の見出しである「企業経営から都市経営まで『人の営み』をよりよいものにするお手伝いをしたい」ということに尽きます。ということで、ここ1カ月ほどの経験を羅列してみると。
エリアマネジメント
We Love 天神協議会という、福岡市の都心部・天神のエリマネに関わり16年が経っています。(生き字引か!?)。先日、全国エリアマネジメントネットワークで、いわゆる「都心部」のエリアマネジメント(まちづくり)してる人たちが集う全国大会が天神で開催され、その事例を見聞きしたり交流したり。
過疎地域と移住とコミュニティ
大分県中津市の耶馬渓の「平田」地区。この過疎しまくってる地域に移住し、空き家をリノベして場づくりやコミュニティが作られている話を聞き、対話を重ねてみたり。
営みの景観デザインとまちの中の居場所
福岡市中央区平尾の住宅街で、平日の朝にFree Coffee(コーヒーを無料で配り、集う人と談笑するという活動)を、実験と称してやってみた10代の女性(現在は20代になってしまった)。この若者がまちづくりについて関心を持ち学んでみて、自分でもまちづくりをやってみたい!と、居場所のような場を住宅街の屋外でつくることで、景観を生み出している話を聞き。
経営を引き継ぎ組織開発を目指す
経営交代して約1年。若手からベテランまでがいる組織を、交代した新しい経営陣でどうまとめていくか?の相談に向き合い、アドバイザーとして対話を重ねたり。
縮小するまちでコミュニティとまちづくりの架け橋に
福岡県大牟田市の「わかもの会議」のコーディネーターをしている関係で、大牟田の歴史・盛衰の背景を紐解き、大牟田の人の気質・風土を言語化したり。
●●づくりに携わる仕事
大学卒業して社会に出たときはフリーターだったのに、『たまたま“そこに居合わせただけ”』な人生な気がしますが、本当にいろんなご縁をいただいたり、タイミングやキッカケをいただいたり、凄まじく日々学ばせてもらいました。
- 場づくり : イベント・講座・研修・学びや対話の場 など
- コミュニティづくり : 活動するチーム・プロジェクトチーム など
- 組織づくり : 継続的な組織運営・組織開発や人材開発 など
- 空間づくり : オフィスやイベント会場 など
- 地域づくり : 住宅街・祭り・ファシリテーション など
- まちづくり : エリアマネジメント・まちのソフト など
全ての領域に関わる体験を重ねさせてもらい、また個人的関心でいろいろ調べたり見たり聞いたり。それぞれで使われる言語はビミョーに違いますが、全て『人の営み』であるから共通点がたくさん見つかります。
おおよそ●●づくりにおいて、『創造・成長・停滞・衰退』のサイクルの「どこ」のことをやるのか?にもよりますが、現場感ある1年周期のサイクルから20〜30年と世代が代わる大きなサイクル、まちのカタチや産業や文化形成にいたるまでの100~150年単位のサイクルまで。
①フロンティア・未開拓もしくは開放
②ゼロ→イチの創造、テーマ・概念・コンテンツの創造
③拡大・成長の経営・ドライブさせる
④広報・プロモート・巻き込み・ブランディング
この①〜④の役割を担えるリソースがあると、●●づくりは前に進みやすい、というのが方程式かのように存在します。
例えば~
都会や大組織だとリソースがたくさんある代わりに、①の不足が起きやすく、②がおもしろくなくていなくなり停滞に向かう。
田舎だと①がたくさんあるけど②〜④が足りない。
ここ10年はインターネットとSNSで、田舎でも②〜④を呼び込める地域や小さな組織も。そのとき、どれだけ「開放」して余白というか関わりシロを作れるか、あるか、が大事。
この言われてみれば当たり前ですが、現在自分がいる・関わってる組織やコミュニティや地域や都市が、「現在どこにいて、①〜④の何が足りないか?」の現状認識が弱いケースが多いし、それが落とし穴なんだろうな、というのがわかってきました。
人材獲得合戦はまだスタート地点
これから日本という国の現実は、ただ人口が減っていくだけではありません。2055年には、戦後直後(1945年ごろ)の「生産年齢人口の数」と同じにまで減るのと、高齢化率はむしろ戦後よりとてもとても高い国に向かうので、日本中で“人”というリソースの奪い合いが凄まじくなっていきます。
現在の文明社会だと、イノベーションが最適解なので、ダイバーシティ&インクルージョンは、外資や大企業だけの話じゃなくて、むしろ中小企業や地方のほうが大事になります。
一方で、簡単に国境を超え人を引き付ける“文化”をどう宿らせるか?がもう1つの答えだと思っていて、とても時間がかかるものの、ここにリソース振り向けた組織や地域や都市は、豊かさを享受しやすいのだろうなと。
よって、現場にある小さな波から、都市の盛衰、時代の変遷までの大波まで、今我々はどこにいるのか?を把握できなければ、ズレた解決法を打ち出してしまい衰退の引き金を引きやすくなっています。要するに、「現状認識」が生き残るカギになってくるなと思っています。
あらゆる経営には迷子がある
1度しかお会いできなかったとある経営者(今年亡くなられた)、そのお会いしたときにこう言われました。
「経営には迷子がある。ゴールがわからない、行き方がわからない、今どこにいるかわからない。この3つをわかるようにしないといけないんです。」
これは真理だなと常々思います。
場づくりや空間づくり
チームづくりや組織づくり
地域づくりから都市のエリアマネジメント まで。
岩永真一という人間の得意であり、きっと才能だと思っている複数の視点から「現状を認識」し、今何をしたら良いか?のよりよい回答を導き出すこと。それをコミュニケーションにデザインしていくこと。この力を使って、多くの●●づくりしたい人たちの役に立ちたい、と改めて思いました。