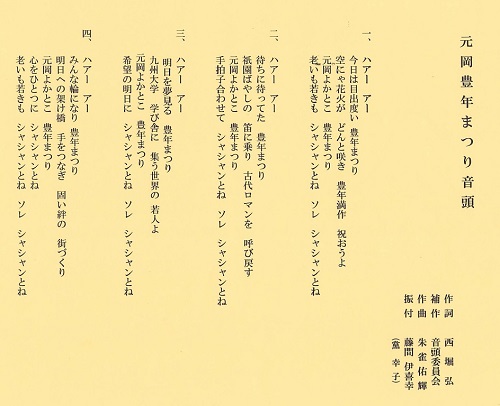北九州市立大学の地域創生学群(という学部)は、地域活動を教育プログラムとして専門にしている学部です。2013年より特任教員として大学教員をさせていただき、今では学群長(いわゆる学部長)になった眞鍋先生も民間企業出身でもあり、僕も民間企業出身者としていろいろお話をさせていただいていますが、2017年度より特別講師という肩書に代わり、関わり方も月に1回程度になりました。そんな北九大・地域創生学群からの視点で「地域活動と大学教育」についてみてみても、この4年とちょっとの間でも変化・進化を感じます。
地方大学がモデルとする事例になった
僕が高校生の頃、地方国立大学は地方とは言えそれでも国立、立派なブランドがありました。ところが少子化の影響や、地方より都市部に人口が集まっている世界的な現象も加わり「地方国立大学はブランド力を弱めてきている」状況でした。文科省も全国の国公立大学に向けて「グローバル人材育成か、独自の研究か、地域人材育成の3つの方針のどれか選びなさい」という指令みたいなものを出し、地方国立大学の大半が「地域人材の育成」に舵を切り始めています。
そこで先進事例となってしまった北九州市立大学のこの地域創生学群に注目が集まり、高知大学や宮崎大学が地域なんちゃら学部を創設、この流れはまだまだ続きそうです。さらには若者人口がまだまだ集まっている福岡都市圏の私立大学にも広がり、九州産業大学も2018年度スタートで地域共創学部の設立を計画(申請中?)のようです。これも実は、北九州市立大学へ相談に来られているのを聞いておりましたので、今後がとても楽しみです!
北九大は開拓者として先を行く?
他の地方国公立大学の情報があまりないので、なんとも言えませんが(笑)冒頭の記事は、毎日新聞に前回の記事「green bird 全国リーダー会議に参加してきました」で北九州チームが統計部門で世界一を取りMVPに2年連続でなったのが取り上げられた記事なのですが、この毎日新聞が北九大の取り組みを追いかけてくださっています。
このようにメディアも絡めたり、講義に多くの企業を参画させてリクルーティングにもつなげるような取り組みをしたり、各先生たちが「大学外へ出て」どんどん進化させようとしています。
これは既存の大学の、既存の研究者として大学の先生をしている人たちには真似できない取り組みでもあると思います。つまり、「地域なんちゃら学部」などは本当に外部ネットワークが必須となるので、新たに教員を外から引っ張って来ないといけなかったりしますが、多くの大学がそのような体制になかったりするので、今後明暗が分かれてきそうですね。
AO入試に地域活動が入ってきた!
そして先日知ったのが、北九大の地域創生学群が、AO入試に向けて「指定事業」なるものを設け、これに参加した高校生はAO入試で加点されるというもの!その指定事業にグリーンバード北九州チームを指定いただき、先日のそうじの日には近隣県から高校生たちが参加しておりました。
いやぁ、グリーンバードを13年もやっている身として、これが教育プログラムになるなんて考えてもいなかったのが4年前で、今度は入試ですか。やっていることはそうじですよ?と不思議な気持ちになりますが、その理由もうなずけます。
地域活動にはいろんな教育的要素がつまっている
簡単に言えばそういうことですね。北九州チームの運営をしている大学生たちは本当にすばらしく、チームワーク・コミュニケーション・リーダーシップ・責任感・最後までやり遂げる・議事を残す・情報を共有する、などなどの社会人としての基礎力みたいなものが培われていくのがわかります。
ということで、これからますますこの地域活動は大学教育に広がりを見せるでしょうし、高校へも広がっていくことが予想されます。
一方でこんな課題もあると思っています。
仮説を立て検証する思考を鍛えないといけない
高校生のときまで理系科目が得意だったにも関わらず、行きたい学部がなく「経営」という言葉に惹かれて文系の学部でもある経営学科に行った自分が言うのもおかしいんですが。大学教員をしていて1つ引っかかりがあるのが、文系の学生ほど「仮説を立てる」「仮説を検証する」「検証した結果、改善する」というのが意外に弱いです。
僕自身は元理系だったからなのか、今でも数学・物理は得意なのですが、この仮説から検証から実践がけっこう得意でして、グリーンバードの活動も、テンジン大学の活動も、これがかなり役だっています。それ以上に、複数の企業のコンサルや広告・販促・集客などのお手伝いの仕事をしたりしますが、大いにこれが役に立ちます。
大学生たちを見てると、大学の講義の中でこれを鍛えるのは実はけっこうハードルが高そうなのがわかっていまして、まだ強制力のある高校時代にこの学習をしっかり積んでおくと後がすごく楽になると思っています。もちろん社会に出てからの話ですが。
大学においても「地域なんちゃら学部」を展開しているところは、これらの部分をどこまで把握できているのかはわかりませんが、北九大の学群長には前に共有しており、課題意識を持っていただいていると思っています。(とは言え、やはり高校時代に文系に絞ってしまった学生たちは難しそう・・・)