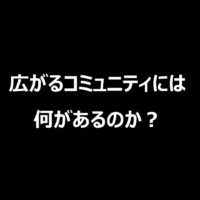22歳の社会人になったときから、働きながら社会活動に関わったり、まちづくりに関わったり。その結果、27歳で独立してフリーランスになって以降、「営業活動」はあまりしていないのに、仕事が少しずつ多様化していき、31歳ごろから仕事が途絶えない「複業」の働き方になってきたので、「複業家」と言い始めたりしていました。43歳の2025年、「副業・兼業」を国も推進していたり、仕事のマッチングをするプラットフォーム会社も多数存在し、「複業」という言葉も一般化の手前あたりまできた世の中になってきました。
そこで今回は、自分自身の経験から「仕事が途絶えない複業人材」について書いてみようと思います。
「複業人材」とは?
そもそも、国が「副業・兼業」を推進する背景には、「地方の人材不足」「事業承継問題」の深刻さで、都会の能力を持て余したプロフェッショナル人材と、地方の企業とをマッチングすることで、「広報・販促・マーケティング」の強化をしたり、「イノベーション」「新規事業開発」をしたり、というのが2019年度ごろから経産省は動いていました。
働き方としては「副業・兼業」なので、基本はリモートワークで月に1~2回ほどリアル対面、など様々なパターンがあるようです。それからコロナが来て、多くの都会のサラリーマンは出社禁止とリモートワークになり、「副業・兼業」を始める人が激増したと、マッチングプラットフォーム会社の方から聞きました。
そして2025年の現在、団塊世代の後期高齢者突入も始まり、医療・介護現場はもちろん、働き方改革による運輸業や、建築・土木などのフィジカルを使う業界では人材不足が深刻化、ITのエンジニアも賃金が高騰するほどの不足で、ほぼ全ての産業で人手不足になってきています。そんな社会課題を解決する働き方として、「複業」を選択する人材への期待が高まっています。
そしてもう1つ。「副業・兼業」を始めたり、「複業」を目指す人が出てきた背景として、「賃金上昇がなかった」時代が長かったことや、ここ1年の新卒の初任給の急上昇があるものの、40・50代は賃金の伸びが少なかったり。さらにそんな上司を見ながら「責任は重くなるのに、給与の伸びもあまりないなら・・・」と、「給与据え置きでも、短い時間で仕事を終えて、自分なりの副業を見つける方がマシ」と考え始める20・30代も多いとか。
と、日本全体で見ると「副業・兼業」や「複業」をする人のニーズは高まっており、その市場もまだまだ大きくなりそうです。この波に「乗っかりたい」個人も企業も、これから多く出てくると思います。
複業人材、副業・兼業のフリーランスの落とし穴
とは言え!
27歳からフリーランスをやってきて、「副業・兼業」や「複業」する人たち、いわゆる「広義のフリーランス人材」が陥りやすい落とし穴があります。
「副業・兼業」も「複業」も、そして「フリーランス」も、専門性を活かした仕事は、ある意味、自分の時間というリソースの切り売りをしている状況です。企業がそれらの人材に発注したその瞬間は、「他に選択肢がない」などから選ばれていた可能性が高いです。それが年月が経つと、企業側も「AIやDX」などの技術的進化が起きたり、そもそもの「経営者・経営陣が交代」したり、そして「担当者が異動」したり、様々な投資を行い進化しており、企業側の方が成長のスピードが速いことが多いです。
広義な意味での「フリーランス人材」の落とし穴は、自分の限られた時間を「可能な限り仕事に振り切って、専門性を活かして稼ぐ」ということが可能な分、そのときは生産性のない「学習」や「自己のアップデート」に時間をかけるインセンティブが発生しにくいところ。よって、30代でデザイン力があって独立したフリーランス人材が、50代になる頃には自身のデザイン力のみで勝負しようとすると、若くフットワークの軽く、最新のトレンドも感覚でよく分かる30代のフリーランスと勝負することになったり、近年ではAIと争う場面も増えてしまい、受注が取れなくなっていくのです。
上記は「クリエイティブ人材」の事例ですが、このような技術革新や競合を意識しながらアップデートの時間を確保し、かつ様々な要望に応え、「高いパフォーマンスを出し続ける」、いわゆる仕事が途絶えない複業人材になることは一朝一夕では実現しないことがわかります。
(上記は、「それはサラリーマンにも言えることだ!」と思いますが、複業人材はより競争の激しい環境にいるので、今回は複業人材に絞ってみていきます)
それでは、「仕事が途絶えない複業人材になる」ための要素を整理していきましょう。
1.社会性の高い働き方をしよう!
記述の通り、「副業・兼業」「複業人材」という広義のフリーランスは、高い専門性を持っていればいるほど、その時間を対価としての金銭に変えるインセンティブが強く働くため、自身の時間を「経済的な価値創造」に振り切りやすい傾向があります。
もちろん、そこで「より高い要望」をもらい、それらに挑戦し続けることでキャリアをステップアップさせていく人もいるでしょう。ですが、多くの「副業・兼業」「複業」の仕事が、企業から切り分けられたタスクを解決する人材として、穴埋めされるように発注するパターンがほとんどです。現状、マッチングプラットフォームの企業では、そのような案件が99%のように思います。
そこで1つオススメしたいのが「社会性の高い複業人材」を目指すこと、です。
「社会性高い複業人材」とは、自身の専門スキルや経験を活かし、複数の企業や組織、プロジェクトに同時に携わることで、経済的な価値創造だけでなく、「社会的な課題解決にも貢献する人材」と定義できます。
発注する企業も、その担当者も、この「社会性が高い」可能性は低く、経済的な価値創造だけでなく、社会や地域をより俯瞰した視点で見ることで、「この仕事の延長に、地域貢献や社会貢献に繋がり、より豊かな社会づくりになる」というビジョンや目標を掲げたり、言語化することでそれを共有することができます。そうなると、仕事の内容や質が少し変化したり、「経済的な価値創造なら今まで通りで良いけど、社会課題の解決を意識したら、このレベルやこの範囲までやりませんか」という提案も可能になってきます。
さらにそのような仕事スタンスが、担当者や企業を動かし、さらに仕事を通じて「社会課題の解決」にアプローチできるという、自身のブランディングにも繋がります。
ではそのような「社会性の高い」人になるためには
●社会課題への意識を持つ
地域の人材不足、産業の衰退、後継者不足、地域活性化など、現代社会が抱える課題への深い理解と関心を持つ。
●企業だけでなく社会への貢献意欲を持つ
自身のスキルを社会のために役立てたいという強い意欲を持ち、目先の利益だけでなく、長期的な視点で社会への貢献を重視する。
●倫理観と責任感を持つ
高い倫理観を持ち、関わる組織やプロジェクトに対して誠実かつ責任感を持って業務を遂行する。
●共創の精神
多様なステークホルダーと連携し、協力しながら課題解決を目指す共創の精神を持つ。
とくに最後の「共創の精神」は、より社会を俯瞰的な視点で見ることでしか見えてこない解決手法で、クライアントとなる企業や自分自身だけでは解決できないときに、他社や地域の自治体、市民などとも組んで取り組むような事業やプロジェクトになります。もうこれだけで、社会的・地域的なインパクトが非常に大きいのです。
2.社会にも貢献できる複業人材の思考やスキル
「社会性の高い」働き方を担保するために、どのような思考やスキルを身に付けた方が良いのか?仕事の依頼が途絶えず、継続的に社会に貢献し続ける複業人材に求められる思考・スキルについても考えてみます。
●思考
・本質探求 : 目の前の問題の本質・根本原因を追究し、解決策を論理的に導き出す思考力。
・俯瞰的な視点: 特定の組織や業界の枠にとらわれず、社会全体の構造や動向を理解し、広い視野で物事を捉える力。
・学習意欲 : 常に新しい知識やスキルを習得し、自己成長を続ける意欲。
・当事者意識 : 社会課題を他人事ではなく、自分自身の問題として捉え、積極的に行動する姿勢。
・長期視点 : 短期的な成果だけでなく、長期的な視点で社会への影響を考慮し、持続可能な解決策を追求する姿勢。
●スキル
・横断スキル : 特定の分野のみの知識や経験だけでなく、業界や業種を超えた知識や経験を持つ。例えば、経営戦略、マーケティング、財務、人事、IT、デザイン、技術開発など、社会全体における業界の位置づけや、企業内を俯瞰して見る視点を持つことができる。
・マネジメントスキル: プロジェクトを計画、実行、管理し、目標達成に導く能力。組織運営、人材育成、リーダーシップなども含む。
・コミュニケーションスキル: 多様な関係者と円滑なコミュニケーションを図り、信頼関係を構築する能力。傾聴力、説明力、交渉力、プレゼンテーション能力など。
・ネットワーキングスキル : 多様な人々との関係性を構築し、維持する能力。人脈形成、紹介、関係性深化など。
・ファシリテーションスキル: 会議やワークショップなどを円滑に進め、参加者の意見を引き出し、合意形成を促す能力。
・異文化理解力 : 異なる文化や価値観を持つ人々を理解し、尊重し、協働する能力。グローバルな視点や多様性への受容性も含む。
・デジタルスキル : 現代社会において不可欠なITツールやデジタル技術を効果的に活用する能力。情報収集、分析、発信、コミュニケーションなど。
ここに上げた思考やスキルを網羅している人材はほぼいないのですが、これらを意識するだけで、一度仕事をすると「この人を経営に近いところに置いておきたい!手放せない!」「でも直接フルタイムで雇用したいけど、できないので複業として絡んで欲しい!」となっていくと思います。
3.ネットワークがものを言う複業人材
最後に、「ネットワーク」について整理します。1の「社会性の高さ」や、2の「思考やスキル」について、このネットワークが土台にないと、自ら一人で身に付けることはほぼ不可能と思っています。人は、他者の影響を非常に受ける生き物です。「どのようなネットワークを持つか?」、それが仕事が途絶えない複業人材を規定してしまう、一番重要なものと言っても良いかもしれません。
通常、大きな組織で働いていても、中小企業で働いていても、「業界の中でのネットワーク」は築きやすいです。専門知識も持ちやすいし、何より共通言語や共通の悩みなど、話しやすい話題も多く、業界内で転職する人も多いからです。
そこでオススメしたいのが
・地域ネットワーク : 自分の住むまち・都市の中で、多様な(自治体、商工会議所、金融機関、NPO、他業種の企業など)繋がりをつくること。中でも、地域社会のキーパーソンとの繋がりコミュニケーション機会を持つことで、地域課題の把握、連携、プロジェクト推進に必要不可欠なネットワークと接続できます。
・コミュニティネットワーク : プライベートにおける趣味や関心事を共有するコミュニティ(出身地、学校、スポーツ、PTA、自治会など)に所属することで、思わぬビジネスチャンスや地域貢献のキッカケになったり、予期せぬ知識や情報が入ってくるよになります。
・オンラインネットワーク : SNS、専門家プラットフォームなどを活用したオンライン上のネットワーク。情報発信、自己PR、機会探索などが用意だったりします。
この中では、比較的簡易でお金も時間もかかりにくいのが「オンラインネットワーク」なものの、やはりオンラインは「似たもの同士」が集まりやすく、選択肢も多いので「自分に合いそうなもの」を自然と選んでしまう傾向があり、そういう意味では「社会性を育てる」ことにあまり向いてなかったりします。
なので、地域社会における「多様な」繋がりをつくることを目指して、複数の異種なコミュニティに所属してみたり、自分が意図していない出会いが生まれやすい、「アウェイな環境」も1つくらい持っておくことも、自身を社会的にアップデートさせるよいキッカケになります。
仕事が途絶えない社会性高い複業人材になるために
最後に、これまでの要素を踏まえ、仕事が途絶えない社会性高い複業人材になるためには、以下の点を意識することも大事なポイントと思っています。
・自己ブランディング
自身の強みや専門性を明確にし、ターゲットとする企業や組織に響くメッセージを発信する。ウェブサイト、SNS、ポートフォリオなどを活用する。
・価値提供の明確化
企業や組織が抱える課題を理解し、自身のスキルでどのように貢献できるかを具体的に提示する。
・実績と事例の蓄積
過去のプロジェクトや業務での成果を具体的な事例としてまとめ、アピール材料とする。
ようするに「情報発信」です。例え、思考もスキルも持っていたとしても、誰にも知られていなかったら「存在しないのと一緒」になりますし、ネットワークがあっても「自分がどんな人か」を発信がなかったら、ただの人と思われてしまいます。
まとめ
「仕事が途絶えない複業人材」として、自分自身を事例に整理したため、「社会性」というワードを持ち出し、そしてそれを軸にまとめてみました。
22歳の社会に出たときは広告業界の営業もしつつ制作にも近い領域の「経験」しかできない状況で、転職も広告業の中で、デザイン制作会社→販促企画会社→WEB制作会社と経験していたものの、その裏側でNPOの活動やまちづくりに関わっていたことで、27歳で独立後、仕事の幅が少しずつ広がり、相談が常に来るようになりました。
もちろん、未経験の領域だと最初はボランティアな部分も多かったりするものの、新たな業界の新たなネットワークに接続できたり、社会的に「自分という存在」を認知してもらえる機会が訪れたり、「経済的な価値創造」だけでなく、「社会課題への意識と貢献活動」という両輪でやっていたことで、福岡・九州という地域社会の中で、様々な相談をいただけるようになってきました。
ときには、ナショナル企業(の福岡支社)から問い合わせがあったと思ったら、なんと近所のパパ友が問い合わせた方の上司だった!ということもあり、一緒にお仕事をすることが即座に決まったり、Aというコミュニティで得た知識や情報が、Bという業界では講演料いただけて話せる素材になったり、「多様なネットワーク」にこそ、様々なチャンスがあることが明確にわかってきました。
今では、仕事として「経営者支援」「人事戦略・採用」「広報」「育成」などの領域の仕事もできるようになり、民間企業の支援も4社(すべて業界違う)ほど行いつつ、福岡テンジン大学や自治体・教育、そしてまちづくりの仕事もしている複業人材になっていると思います。
社会の中で、常に価値を生み出し、経済的な価値創造だけでなく、社会に貢献しながら「充実した複業キャリア」を築きたい!と思っている方の、参考に少しでもなれば幸いです。