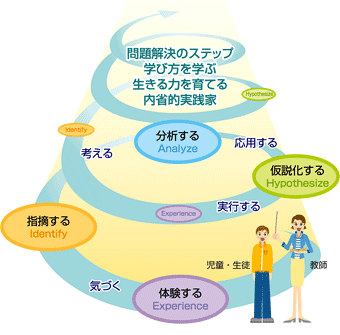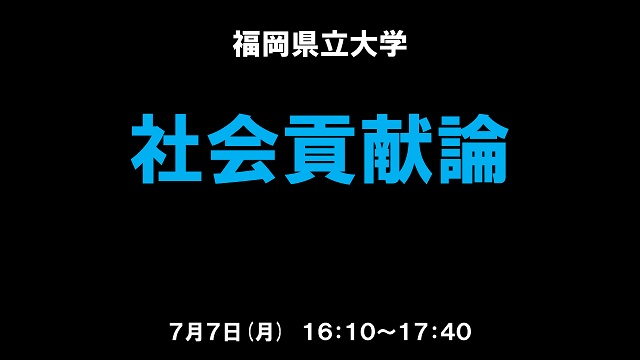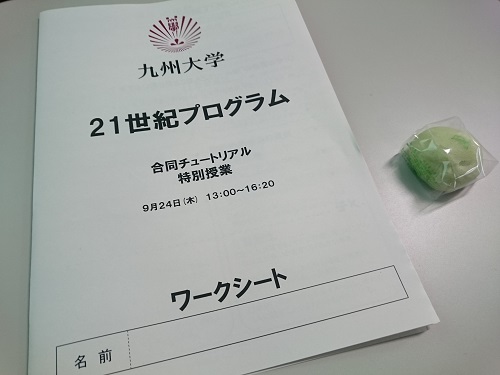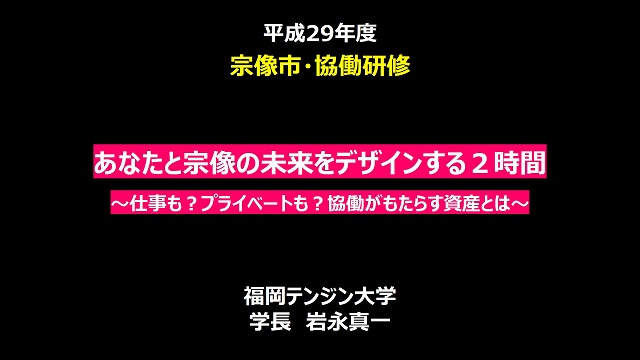福岡にあるとある施設を管理している会社より、このブログからお問合せをいただいた。いろんな会社・テナントが入居しているものの、その入居社(者)たちのいわゆる町内会的な「会」が機能してないので、ファシリテーターをしてほしい、と。
さっそく事前ヒアリングに行き、会の会長・副会長など役員の方々(全員会社は別々)にお話しを伺った。会へはその施設に入った時点で強制的に入会が義務づけられているものの(でもそんな決まりはなく、慣例化?)、最近は定例化している会議への参加者も減り、「会が硬直」状態になってしまったそうだ。そこで「そもそもの原因」を探ってみると、その町内会的な「会」が“できた目的”“何のために存在するのか”“何をするのか”“どんな成果を出すのか”が無い。正確には無いというより、引き継がれてない、明文化されてなかったのだ。
地域とは違う、施設内の企業村の町内会
そうなると、住民でもない昼間しかその施設に働きにきていない、ましてや多くがサラリーマンのいち役割として「会」に出席している参加者にとっては、「この会って何のためにあって、何をやるところなのか」がわからない。わからないから、アイデアも意見も出てこない。年数をかけて負の連鎖が続き、いよいよ内部の力だけでは登れないほどの落とし穴にハマってしまったようだ。
福岡市では戦後ひたすら人口が増加し、その人口増加を吸収していったのが集合住宅、いわゆるアパートやマンションだが、近年は再開発で大型マンションがどんどん乱立して、いまだに人口を吸収し続けている。転勤族も多く、分譲ではなく賃貸の需要も多いため、どうしても「仮暮らしの人」の割合も多いし、一人暮らしも多い(若者も、高齢者も)。
※東京カンテイ「政令指定都市マンション化率2008年」と、総務省統計局「平成20年住宅・土地統計調査2008年」によると、福岡市は政令市中トップのマンション化率なのに、政令市中トップで持ち家率が低い。
こうなると、ただでさえ福岡市内の町内会は「地域が自分事」になる住民が少ないので活性化しにくい。これと似た環境が今回の施設で起きてしまっていたというのだ。
企業村の町内会でファシリテーション?
そこで今回初めて外部の、しかも進行役で?会議を?と、きっと参加者にとってはわけのわからないままファシリテーター役として僕が登場することに。そう、文脈が繋がらず、楽しそうなお祭りやイベントでもなく、これはビジネスにおける生産的なことをする会議なはずなのに、目的もすることもよくわからないまま「外部の人きちゃったよ」状態からスタートする現場。
事前ヒアリングで「根本的な原因」がわかったので、会の目的も定まってないのにファシリテーションをしても付け焼刃だ。しかも参加者にとっては、これまでの固い空気の会を引きずっての今回に「なんかよくわからない外部の人」が登場。
全員が共通認識を持つところがスタート地点
参加者同士の横の繋がりもあまり強くなければ、そもそも会では意見やアイデアが全く出なかったので、まずはその見えない壁を壊す、無意識に引かれていた境界線を溶かすところからスタート。そして、「この会の目的、存在意義、何を目指す会なのかが明確じゃないからこうなるんだ」を全員が認識し課題意識を持ってもらうことをゴールに、声を出してもらう場づくりをした。
「フラットな関係性と、ほどよい人間関係の距離感」が一瞬でもつくられると、話しやすく意見が言いやすいことが体験でき、事前ヒアリングのときに参加していた役員の方は「今までで一番、参加した充実感があった」と終わったあとに言っていた。
とあるテナントであり会の会長でもある方も、「問題がどこにあるか」が最重要な事項として認識できたのか「明文化を進めよう!やろう!」ということになった。袋小路からは抜け出し、この「とある施設のテナントによる町内会のような会」は新たなスタート地点に立つことができたように思う。
そしてこれからもう少し、伴走することにもなりそうなので、引き続き「対話型会議」を目指して外部からできるかぎりのことをやってみようと思う。
対話のある場づくりをファシリテーションしていくには?