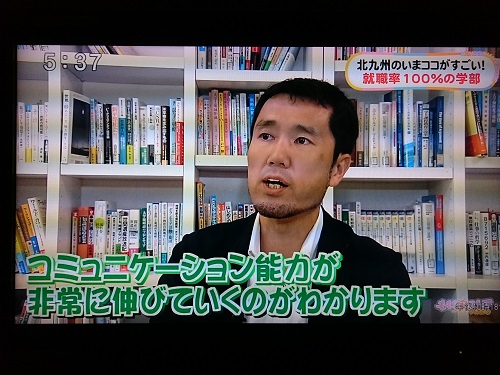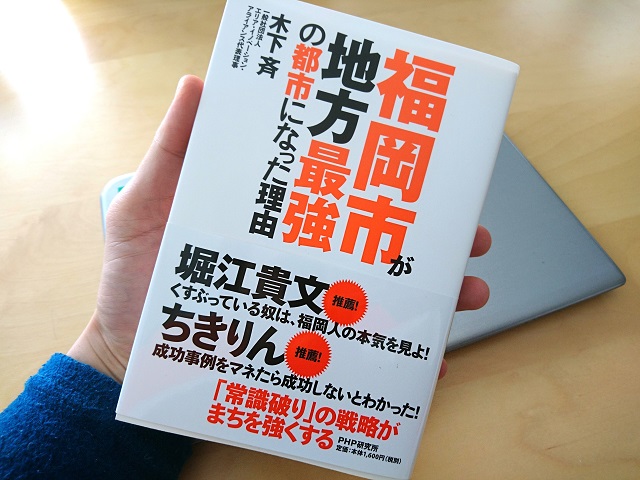先日の8月31日(木)、福岡市科学館ネットワーク「サイエンスカフェ」にて、博報堂の鷲尾さんをゲストに迎えたイベントでファシリテーターを務めました。ヨーロッパのドナウ川が貫くオーストリア第3の都市リンツ。ヒトラーが生まれたというこの人口20万人ほどの街で、毎年9月に開催される「アルスエレクトロニカ」というアート×テクノロジーのフェスがすごいです!!
1979年からはじまったフェスが都市とともに進化中
博報堂の本社で勤務されていて、カメラも撮るという鷲尾さん、最初に「アルスエレクトロニカ」の存在を知ったのは、書籍「みんな、どんなふうに働いて生きてゆくの?」とか「いま、地方で生きるということ
」の著者、西村佳哲さんから「アルスエレクトロニカを見ておいた方が良い」と言われたからだそうです。
情報を人びとに届ける”メディア”としてのフェスティバルの役割などを研究しようと、2006年(だったかな?)から毎年、オーストリアのリンツに博報堂の仕事として行くようになった鷲尾さんが書いた「アルスエレクトロニカの挑戦: なぜオーストリアの地方都市で行われるアートフェスティバルに、世界中から人々が集まるのか」が、まちづくり(主にソフト面)とか、地域活性とか、地域人材育成とかの分野の仕事をしている人や、博物館・美術館などミュージアム系の仕事をしている人、そしてテクノロジー関係の仕事をしている人たちには必読な本です。
冒頭の写真は、その本の中でも登場するステキな写真!(撮影はもちろん鷲尾さん)

これは市民のパレードですが、ただのパレードではなく、スマホでみんなが参加型で撮影した写真で1つの映画?動画?がつくられるのだそうです。そうです、このアルスエレクトロニカというアートフェスの最大の特徴が「市民参加型」なのです。
1979年、4人の民間人がはじめた小さなアートフェスが、次第にリンツ内外、いや、世界から注目を浴び始め、1980年代後半にようやくリンツ市が積極的に支援・参画をはじめ、今では毎年世界中からも観光客がやってくるものになっています。それだけじゃない、年に一度開かれるコンテストでは「ビジネスになるかわからないけど、それでも尖ったアイデアやテクノロジーなどの作品が集まる最先端のコンテスト」になっているのです。日本人も多くがエントリーし、賞を獲得しています。
このコンテストの審査員は2年ずつで交代していく仕組みのようですが、なんと鷲尾さんも審査員をしていたそうです。
リンツ市民のマインドが変化!まちづくりってこういうことだと思った
今回のサイエンスカフェで鷲尾さんが紹介してくれた出来事にこのようなことがありました。「審査員として、リンツ市内のカフェで作品についての議論をしていた。そしたら通りすがりのオジサンが議論に入ってきて、”あの作品は俺からすれば~”と持論を展開、議論に混ざっていった」そうです。
約40年近く続き、年に1度のアートフェスだけでなく、市民にもアートとテクノロジーを日常的なものとしてもらうために「アルスエレクトロニカ・センター」ができ、市民参加型の多くのプログラムやワークショップが毎年展開され、世界最先端の、まだビジネス化・社会化するかどうかもわからないテクノロジーや作品が集結し、コンテストも市民に開かれていくとどうなるか?2009年には欧州文化首都も獲得し、ユネスコ・クリエイティブ・シティズ(創造都市)にもなると、市民は「リンツという街に愛着だけでなく、誇りと責任も持つ」ということ。
何より、このアートフェスが進化して継続され、恒常的なセンターまでできたことにより・・・。世界中のテクノロジーの会社が、アルスエレクトロニカで販促イベント(実験)したり、ビジネスチャンスとしてネットワークしたりまでが生まれ、2009年の世界中をビビらせたリーマンショックの影響もほぼ受けず、若者の失業率は低く安定し、何より「街の人口よりも多くの雇用を創出」している点に一番の衝撃を感じました。
こんなクリエイティブで、進化や変化への恐れより歓迎をする市民の文化をつくり、ビジネスも雇用も生まれ、住む人の自主性や創造性を掻き立ててくれる都市、日本にあるだろうか?もちろん、リンツの高等教育も評価が高いとか。子育てにも絶対に良いと想像する。
で、結局行ったことも見たこともない、本読んで話を聞いただけの僕の文章では結局「アルスエレクトロニカってなんなの?」ってなるので、下記の行った方のレポートを貼り付けておきます!(検索して出てきました)
・アルス・エレクトロニカ(Ars Electronica)体験レポート 2016【前編】
・アルス・エレクトロニカ(Ars Electronica)体験レポート 2016【後編】
この方が書いている、以下のコメントに賛同!!(行ったことないのに・・・)
何度も実験を繰り返して、価値の存在を証明し、継続して人の繋がり構築し、持続的に成長していることは確かだ。実験は閉じた研究室の中でなく、街と人を巻き込んで実社会の中で行われ、成果は世界中に還元されている。アルスとは、実験場であり、社交場であり、メディアだ。
アルスエレクトロニカから学ぶ”ひとづくり”と”まちづくり”
鷲尾さんが登壇する前の事前打合せでいろいろお話をしました。もちろん「アルスエレクトロニカの挑戦: なぜオーストリアの地方都市で行われるアートフェスティバルに、世界中から人々が集まるのか」は事前に読んでいたのですが、より深い考察ができました。
リンツがこのような都市になったのは、「アルスエレクトロニカ」があったからではない。もしかしたらキッカケにはなったかもしれないが、結果として40年近く続き、このような都市になれたのはそれなりの「土台」があったから。氷山の一角で、見えてる部分が「アルスエレクトロニカ」だ!という感覚になりました。
さらに鷲尾さんは登壇中に「これが大事!」と。
・社会資本、人的資本にシフトさせる
・文化政策=社会政策を結び付ける
・社会的空間(ソーシャルスペース)を確保する
・ネットワーク志向を徹底する
これを掲げてまちづくりをしている自治体は見たことがないです。つまり、日本にはまだまだアルスエレクトロニカのようなものが生まれ、育っていく都市は現れそうにありません。きっと世界中、そうなのかもしれません。だから、アルスエレクトロニカに「自分の都市、国では評価すらしてもらえないけど、リンツに行けば評価してもらえるかもしれない」という、ある意味世界最先端の人たちが集まるのです。それが市民参加型でイノベーションをおこしていく。
だから、鷲尾さんも毎年、企業の方で興味を持った方を連れていくそうです。そして今年は、日本のとある自治体の方々も連れていくとか!動き出してますね~。
都市だけでなく、もっと小さい組織・企業などでも、イノベーションという言葉が流行りつつありますが、アルスエレクトロニカに学ぶところは非常にあると思います!と、前日にFacebookでイベントの告知をしていたら、「グッデイならできる♪」でおなじみ、ホームセンターグッデイの社長がコメントくださり、アルスエレクトロニカに視察に行ってました!さらに共同開発で商品つくってた!!
世界で今、一番訪れてみたい都市がリンツになりました。
アルスエレクトロニカ、そしてリンツの都市に学ぶものがまだまだある!よかったら読んでみてください。